
沖縄(おきなわ)の名前の由来
■ もとの言葉と意味
「沖縄」という名前は、古い琉球(りゅうきゅう)の言葉にルーツがある。
- 「沖(おき)」= 海の向こう、海に離れた場所
- 「縄(なわ)」= 本来は「島」という意味を持つ言葉(縄のように長く連なったもの、あるいは文化的なつながりを指す)
つまり、「沖縄」という名前は 「沖にある島々」 という意味を持っていると考えられている。
■ 歴史的な記録
初めて「沖縄」という名前が登場するのは、中国の歴史書『冊封使録(さっぽうしろく)』などの記録である。
- 1372年、琉球が中国に朝貢(ちょうこう)を始めた時代に、「沖縄(オキナワ)」という表記が確認できる。
- ただし、当時の発音は「ウチナ」とか「ウチナー」に近かったと言われる。
- これは現在でも沖縄の人たちが自分たちの島を呼ぶときに「ウチナー」と言うことに名残が残っている。
■ さらに深い説
「沖縄」という呼び方にはいくつか説がある。
- 航海用語説
沖に浮かぶ「道標(みちしるべ)」のような島々だったため、「沖の縄(目印)」と呼ばれた。 - 島伝説説
昔、琉球には「オキノワタリ」という神話の島があるとされ、そこから「沖縄」という名前が派生したという説もある。 - 地形説
南西諸島(沖縄諸島を含む)は細長く連なっているので、「縄のような形をしている沖の島々」という意味だ、という説もある。
■ まとめると
- 「沖」=本土から見て海の向こう側
- 「縄」=島や連なりの意味
- 古くは「ウチナ」「ウチナー」と呼ばれ、現在の「沖縄」という漢字表記に定着
- 中国との外交(冊封体制)の中で記録され、国際的にも知られるようになった
琉球の名前の由来
■ 「琉球」の最初の登場
「琉球」という名前は、日本ではなく、古代中国の文献に最初に登場する。
- 最古の記録は、『隋書(ずいしょ)』(7世紀・隋の歴史書)に出てくる。
- そこでは「流求(るきゅう)」という字で表記されている。
- さらに後の時代には、「琉球」と書かれるようになった(唐代以降)。
■ 漢字表記と意味
- 「琉」は「美しい宝石(瑠璃・ラピスラズリ)」を意味します。
- 「球」は「丸いもの、珠玉」を意味します。
つまり、「琉球」という字面だけを見ると、「美しい宝石のような島」というニュアンスになる。
これは、当時の中国の人々が、琉球を「南の海に浮かぶ美しく神秘的な島」とイメージして名づけた可能性が高い。
■ では、なぜ「流求」→「琉球」になった?
もともとの「流求(るきゅう)」という表記は、地名の音をそのまま漢字に当てたもの(音訳)であった。
- 当時、琉球の人たち自身は自分たちを「ルチュー」とか「ルチュウ」に近い発音で呼んでいたとも考えられている。
- 「ルチュー」→「ルキュー」→「リュウキュウ」と、中国側で聞き取って漢字をあてはめたわけである。
- 「流求」だと少し印象が悪い(流れて求める=流浪者みたい)ので、後に「琉球」という美しいイメージの漢字に改められた。
これは、当時の中国王朝が周辺国を美しく飾った名前で呼ぶ習慣(冊封体制)にも合致している。
■ 琉球=どこを指していた?
最初の頃、中国の記録にある「琉球」は、今の沖縄本島だけを指していたわけではない説もある。
- フィリピンや台湾の島々を含む「南の島々のどこか」と漠然と理解されていた。
- 時代が進むにつれて、現在の沖縄・琉球諸島が特定されていった。
- 特に14世紀以降、「琉球」と言えば沖縄本島とその周辺を指すようになった。
■ まとめ
- 最初は「流求(るきゅう)」として登場(隋書・7世紀)
- 音訳であり、地元語「ルチュー」に由来
- 後に「琉球」という美しい漢字に変更
- 「南の美しい島」というイメージで呼ばれるようになった
- 時代が進むごとに「琉球=沖縄」という認識が確立していった
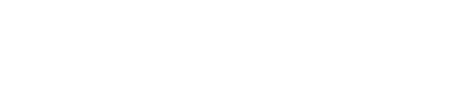





コメント