
沖縄の戦後の基地政策は、沖縄全体、そして特に沖縄市(旧・コザ市)に大きな影響を与えてきた。以下にその流れと主要な要点をわかりやすく解説する。
戦後すぐ:米軍統治と基地の強制接収(1945〜1950年代)
沖縄戦後、アメリカ軍が直接統治を開始
- 1945年、沖縄戦が終結すると、アメリカ軍が沖縄本島全体を占領。
- その後、沖縄は1972年までアメリカの軍政下(琉球政府時代)に置かれる。
土地の強制接収(いわゆる「銃剣とブルドーザー」)
- 米軍は、住民に十分な説明や補償を行わないまま、農地・集落を強制的に接収。
- 家や畑をブルドーザーで潰し、フェンスを設置して基地化。
- 沖縄市を含む中部地域では、特に嘉手納基地・キャンプフォスターの拡張で多くの土地が奪われた。
基地と経済の依存(1950〜60年代)
基地による雇用と収入
- 米軍基地では、清掃員、ガードマン、土木作業員、バーやクラブ経営など、数万人の沖縄県民が雇用された。
- 基地の存在は経済的な恩恵も生み、「基地経済」と呼ばれる仕組みが生まれた。
だが同時に…
- 飲酒運転、米兵による事件事故、土地収奪問題、騒音被害など深刻な社会問題も生じた。
- 「表の顔:経済依存、裏の顔:生活被害」という二面性が生まれる。
住民の反発と事件:コザ暴動(1970)
- 1970年、沖縄市(当時はコザ市)で米兵による交通事故の処理に対する不満が爆発。
- 数千人の住民が暴動を起こし、米軍車両を焼き払うという「コザ暴動」が発生。
- 基地に依存しながらも、反発を抱くという矛盾が表面化。
沖縄の本土復帰と「日本の基地政策」へ(1972年〜)
沖縄返還(1972年)
- 沖縄は日本に返還され、行政的には本土と統合。
- だが、基地の大部分はそのまま残され、日本政府とアメリカ政府の安全保障条約(安保体制)に組み込まれる。
基地交付金・基地使用協定
- 日本政府は、地元自治体に「基地交付金(迷惑料のようなもの)」を交付し、基地容認の姿勢を取らせようとする。
- 地元は財政支援を受ける代わりに、基地問題を簡単には解決できない構造に。
現代:返還と再開発、そして課題
基地の一部返還と跡地利用
- 近年、嘉手納基地などの一部施設の返還が進行中。
- 跡地には商業施設(例:イオンモール沖縄ライカムなど)や住宅、教育施設が整備されつつある。
それでも残る問題
- 沖縄には全国の米軍専用施設の約70%が集中。
- 騒音、事故、事件、環境汚染(PFASなど)など、依然として基地による影響は大きい。
まとめ:戦後の基地政策の本質
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 経済的恩恵 | 雇用と収入源としての役割 |
| 社会的負担 | 騒音、事件、事故、土地問題 |
| 政治的構造 | 日本政府と米軍による安全保障体制 |
| 市民の意識 | 「基地なくして成り立たない」が「基地のせいで苦しむ」 |
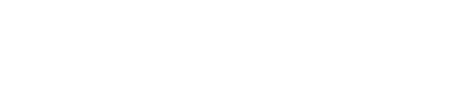





コメント