
「ゆいまーる(結まーる)」とは、沖縄の伝統的な助け合いの精神・仕組みを指す言葉である。
漢字で書くと「結まーる」で、「結(ゆい)」は「結びつき、協力」「まーる」は沖縄方言で「回る」「循環する」という意味が含まれている。
ゆいまーるの精神とは?
簡単にいうと、
- みんなで助け合いながら生きる
- 困ったときはお互いさま
- お金ではなく心のつながりで成り立つ協力関係
という考え方。
具体的にはどういうもの?
昔の沖縄では、例えば
- 家を建てるとき
- 畑を耕すとき
- 祭りや共同作業をするとき などに、村の人たちが無償で助け合った。
そして、助けてもらった人は、別の誰かが困っているときにまた手を貸す。つまり恩返しではなく「恩送り」の形で、助け合いの輪を広げていくのが特徴。
これにより、沖縄の人々は自然な形で共同体意識(チーム意識)を育み、厳しい自然環境や社会状況の中でも、支え合って生きる力を強めてきた。
現代における「ゆいまーる」
今でも沖縄では、地域コミュニティの支え合いやボランティア活動の精神にこの「ゆいまーる」が生きている。
また、福祉や介護、町づくり、地元企業の取り組みなどでも「ゆいまーる精神」を大事にしているところが多い。
そもそも「結(ゆい)」とは何か?
沖縄だけでなく、もともと日本各地(特に農村部)には「結(ゆい)」という助け合いの仕組みがあった。
たとえば、田植え、稲刈り、家づくり、祭りの準備など、大人数の手が必要なときに、近所の人たちが協力し合う組織や風習のこと。
沖縄ではこれが特に深く生活文化に根付いていて、「ゆいまーる」という独特の形に発展した。
沖縄の「ゆいまーる」の独自性
沖縄の「ゆいまーる」が本土の「結」と違う特徴は、いくつかある。
- 見返りを求めない
例えば、「手伝ったからこれだけのお金を払って」みたいな金銭的なやりとりは基本ない。
あくまで「人として当たり前」という自然な感覚で動く。 - 循環する精神
「助けた相手から直接返してもらう」のではなく、「困っている別の誰かを助ける」という形で回ってくる。
これが「まーる(回る)」の意味につながっている。 - コミュニティを守るための知恵
台風など自然災害が多かった沖縄では、単独では生き残れない環境だったため、助け合うことが生存戦略でもあった。
「もやい」との違い
「もやい」という言葉もよく聞くかもしれない。
「もやい」は、特に奄美群島や鹿児島県周辺で使われる言葉で、こちらも助け合いの意味だが、
- 「もやい」は比較的、経済的な互助組織(例えば共同でお金を出し合う、貸し合う)に発展しやすい。
- 「ゆいまーる」は、労働や心の助け合いに重きがある。 という違いが指摘される。
歴史背景
沖縄は、かつて「琉球王国」という独自の国家だったこともあり、独自の村落共同体制度があった。
その中で「ムラ」(村)が重要な社会単位となり、「個人」よりも「集団」で生きる文化が根付いた。
農業中心の社会では、「1人で畑仕事はできない」→「みんなで協力しないと暮らせない」というリアルな事情があった。
現代的な「ゆいまーる」
今は農作業のために「ゆいまーる」する機会は減りましたが、たとえば
- 町内会の活動
- 高齢者サポート
- 子ども食堂
- ボランティアグループ
- シェアハウス、コミュニティビジネス などで、「ゆいまーる的な精神」が生き続けている。
たとえば、沖縄では「ゆいまーる型福祉」と言って、介護や障害者支援の現場でも、「できる人ができる範囲で支え合う」という仕組みが積極的に取り入れられている。
地域福祉活動「ゆいまーる型福祉」
沖縄県内では、高齢化が進む中、行政の福祉サービスだけではカバーしきれない問題に対して、地域住民同士で助け合う活動が広がっている。
たとえば、
- 近所の高齢者のお宅に定期的に様子を見に行く
- ちょっとした家の修理や買い物を手伝う
- 地域サロンで集まって食事やおしゃべりを楽しむ
など、「専門職じゃないけど、できることを無理なく支え合う」スタイル。
これを「ゆいまーる型福祉」と呼んでいる自治体もある。
シェアハウス「ゆいまーるシリーズ」
沖縄発で、全国にも展開している「ゆいまーるシリーズ」という高齢者向けシェアハウスがある。
普通の老人ホームとは違って、
- 自由に暮らしながら
- 住民同士がちょっとずつ支え合い
- 必要なサポートだけ受けられる
という形で「できるだけ自立した生活を保つ」ことを目指している。
ここでも「ゆいまーる精神」が生きていて、住民同士が自然に助け合う文化が根付いている。
地域通貨「ゆいまーる券」
一部の沖縄の地域では、地域内でだけ使える「地域通貨(地域マネー)」を作り、
「誰かの手伝いをするとゆいまーる券がもらえる」
「ゆいまーる券で別のサービスを受けられる」
という形で、地域内の助け合いを活性化しようとする試みもあった。
これは「お金」でありながら、営利目的ではなく、助け合いを促進するための工夫である。
子育て支援・子ども食堂
沖縄では、地域ぐるみで子どもを育てる文化が今も強いです。
最近増えている子ども食堂(無料または安価で子どもに食事を提供する場)でも、
- ボランティアでご飯を作る人
- 勉強を教える大学生
- 場所を提供する企業や個人 などがゆいまーる的に支え合って成り立っています。
災害時の支え合い
台風など災害が多い沖縄では、災害時にも「ゆいまーる精神」が発揮さる。
例えば、
- 倒れた木をみんなで片づける
- 停電時に電源を分け合う
- 食料や水を融通し合う といった助け合いがごく自然に行われます。
これも、「いざというときはお互いさま」という意識が根付いているからこそできること。
現代のゆいまーるは、「農作業の手伝い」だけじゃなく、福祉、教育、災害支援、地域通貨、シェアハウスなど、いろんな形で生き続けている。🌈
【高齢者向け共同住宅】
「ゆいまーる那須」プロジェクト(栃木県那須町)
沖縄発ではないですが、「沖縄のゆいまーる精神」をモデルにして成功しているすごく有名な事例である。
- 元気な高齢者たちが集まって、一つの敷地内で自立した生活を送りながら、
体が不自由になったら住民同士で支え合う。 - 施設ではないので、管理されるのではなく、自分たちで運営する。
- 看取りまで行うことを前提に、「最後まで自分らしく生きる」ことを大事にしている。
ポイントは、「高齢者の孤立を防ぎ、無理なく自然に支え合える環境づくり」。
「福祉」や「介護」というより「人生を豊かにするための共同体」という発想。
この仕組みは今、全国に広がっていて、「ゆいまーる型シェアハウス」として多くのメディアにも取り上げられている。
【地域福祉活動】
「ゆいまーる糸満」プロジェクト(沖縄県糸満市)
- 糸満市では「高齢者ができるだけ住み慣れた地域で暮らし続ける」ために、地域ボランティアと行政、NPO、企業が連携して、福祉サポートネットワークを作った。
- 内容は、
- 高齢者宅への見守り訪問
- ちょっとした日常支援(ゴミ出し、買い物代行など)
- 健康づくり教室の開催
- 孤立防止のための地域サロン など。
行政主導ではなく、地域住民が主役というのが大きなポイントです!
ここでも「できる人が、できることを、できる範囲で」が合言葉になっています。
この取り組みは、全国の自治体からも視察が来るほど注目されている。
【地域通貨】
「ゆいまーる券」(沖縄県本部町)
- 本部町では、町内でのボランティア活動に対して「ゆいまーる券」というポイントを発行。
- たまったゆいまーる券は、地元のお店で買い物できたり、公共施設の使用料に充てられたりする。
- お金を稼ぐためではなく、「地域の役に立つことをした人が得をする」仕組み。
これは、助け合いの精神を現代のシステムに合わせた工夫の例。
地域の経済も回るし、住民同士の交流も増えるし、いいことづくめ。
【子育て支援】
「ゆいまーる子ども広場」(沖縄市)
- 子育て中の親たちが自主的に集まって作った子ども広場。
- 保育士や専門スタッフではなく、地域のおばあちゃんたちがボランティアで参加。
- 子どもだけでなく、親もリラックスして交流できる場所になっている。
「困っている人を助ける」だけじゃなく、
「みんなで楽しく支え合う場所を作る」というのが、ゆいまーるらしさ🌿
成功している共通点は?
- 「制度」よりも「人のつながり」を重視している
- 完璧を求めず、「できる範囲でOK」というゆるやかさ
- 助ける・助けられるの関係を固定しない(立場が固定されない)
- 自主性(強制ではない)
- 小さな単位から広がる(いきなり大きな組織にしない)
これがうまく回っている理由である。✨
ゆいまーる的な組織づくりのコツ
「役割固定」ではなく「自然発生的な役割分担」
- 「あなたはリーダー」「あなたはサポート」と最初からカッチリ決めない。
- 自然に得意な人が得意なことを引き受けるスタイル。
- 誰かが困っていたら「たまたま手が空いてる人がサポートする」くらいの流動性を大事にします。
✏️ ポイント:役割は「生まれるもの」であって「割り当てるもの」じゃない!
「できることをできる範囲で」というゆるさ
- 強制しない。「無理だったら無理でOK」。
- 「完璧にやること」を求めない。
- みんなの「小さな力」の積み重ねを信じる。
✏️ ポイント:「一緒にやってる」感が大事で、「成果主義」じゃない!
「助ける側」「助けられる側」を固定しない
- 今日はあなたを助けるけど、明日はあなたに助けてもらうかも、という相互性。
- 一方的な支援じゃないから、上下関係が生まれにくい。
- プライドを守りながら支え合える。
✏️ ポイント:みんなが「支える側」と「支えられる側」を行ったり来たりするのが自然。
小さな成功体験を大事にする
- いきなり大きな目標を掲げない。
- 「今日は〇〇さんのお手伝いができたね」みたいな小さな達成感を共有していく。
- 成功をみんなで喜ぶ文化を作る。
✏️ ポイント:「やってよかった」「嬉しかった」を積み重ねる!
信頼を前提にスタートする
- 「ルール」や「契約」でがんじがらめにしない。
- 最初から信頼して始める(失敗を前提にしない)。
- 問題が起きたら、その都度みんなで話し合って柔軟に解決する。
✏️ ポイント:最初に「信用できるかどうか」を疑わない。
みんなでごはんを食べる(超重要)
- 意外に思うかもしれないけど、沖縄のゆいまーる精神を支えているのは一緒に食べる文化。
- 小さな集まりでも「お茶しよう」「お昼食べながらやろう」みたいに、食を共有すると、一気に距離が縮まる。
✏️ ポイント:「仕事」よりも「時間を共有する」ことが仲間意識を強める。
まとめイメージ
✨ ゆいまーる的組織とは…
- ゆるやかに
- 自然に
- 相互に
- 小さな積み重ねで
- 信頼をベースに
- 楽しく
育てていく「生きものみたいな組織」である。
おすすめ
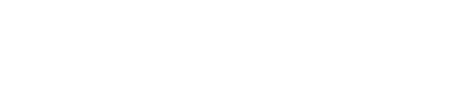





コメント