
「ひめゆりの塔(ひめゆりのとう)」は、沖縄戦で亡くなった「ひめゆり学徒隊」と呼ばれる女子学生たちを慰霊するために建てられた慰霊碑。日本の沖縄県糸満市にあり、戦争の悲惨さを伝える重要な歴史的・教育的な場所である。
ひめゆり学徒隊とは?
「ひめゆり学徒隊」は、沖縄県立第一高等女学校と沖縄師範学校女子部の生徒と教職員のうち、動員された女子学生たちのことを指す。
- 動員された人数:学生約222名、教師18名
- 動員の時期:1945年3月末から6月にかけての沖縄戦
- 任務:野戦病院(壕やトンネル内)での看護や衛生作業、雑務など
- 年齢:15歳〜19歳くらいの少女たち
沖縄戦と悲劇
沖縄戦は日本本土決戦の前哨戦として、アメリカ軍が沖縄本島に上陸して行われた激戦(1945年3月〜6月)。市民を巻き込む大規模な戦闘となった。
ひめゆり学徒隊は、南部の陣地(特に南風原陸軍病院やその後の野戦壕)で看護活動に従事していたが、戦局が悪化すると野戦病院が解散され、学徒たちは戦場に放り出された。
- 死者数:ひめゆり学徒隊のうち、123名の生徒と13名の教師が戦死。
- 死因:砲撃、爆弾、自決を強要された者も含まれる。
ひめゆりの塔
「ひめゆりの塔」は、戦後間もない昭和21年に付近の収容所にいた村民たちの手によって建立されたといわれている。
物資不足であることや沖縄の統治下であったことなどから、高さ数十cmのこぢんまりとした石碑となっているが、この塔は今でも大切に保存され続けている。
そんな「ひめゆりの塔」が建っている場所は、かつて多くのひめゆり学徒や軍人、住民などが身を寄せていた「伊原第3外科壕」の跡地である。
ここは解散命令を受けた翌日に米兵の毒ガス攻撃を受けて、80人が犠牲となった場所だといわれている。
さらに当時の状況を後世に伝えるために、「ひめゆり平和祈念館」も開館し、現在も多くの人が訪れる場所となっている。また、「ひめゆり学徒隊」の御霊は、他の戦死者の英霊とともに靖国神社にて祀られている。
同様の学徒隊について
当時動員された高等女学校は、ひめゆりの他にも複数あった。
最も動員数が多かったひめゆり学徒隊が最も名が知られているが、他にもひめゆりと同じように動員されて負傷兵の世話をしていた学徒隊があった。
それが「白梅学徒隊」「瑞泉学徒隊」「ふじ学徒隊」「なごらん学徒隊」「梯梧学徒隊」「宮古高女学徒隊」「八重山高女学徒隊」である。
これらの女学生から成る学徒隊は、いずれも「ひめゆり学徒隊」と同じく、看護助手として野戦病院に配属されていた。
「ひめゆり学徒隊」では南部撤退までに死者が出なかったという話もあるが、他の学徒隊では、水汲みの途中で手榴弾で命を落とした生徒や病死した生徒も多数いたそうである。
中には伝染病に感染した生徒が出た壕もあり、感染者は壕の最奥にある隔離室に入れられていたという。
そして、やがてどの学徒隊にもひめゆり学徒隊のように解散命令が出され、このときに多くの生徒や引率の教師が命を落とした。
沖縄戦で動員されて非業の死を遂げたのは、ひめゆり学徒隊だけでなく、沖縄県にあった女学校の教員・生徒から結成された他の学徒隊でも同じことだったのだ。
中には戦死者が数%にとどまった学徒隊もあったが、ひめゆり学徒隊・瑞泉学徒隊・梯梧学徒隊では全体数の半数を超える戦死者が出ている。そして、戦後には「ひめゆりの塔」のように慰霊塔が立てられた学徒隊も複数あった。
- 建立年:1946年(戦後すぐ)
- 場所:沖縄県糸満市伊原
- 特徴:
- 実際に多くの生徒が亡くなった壕(伊原第三外科壕)の跡地に建てられている
- 慰霊碑には戦死した生徒・教師の名前が刻まれている
- 周辺には「ひめゆり平和祈念資料館」も併設されており、当時の資料や証言、遺品などを見ることができる
現代へのメッセージ
ひめゆりの塔と資料館は、沖縄戦を語り継ぎ、戦争の悲惨さと平和の大切さを学ぶ場所として、多くの人々が訪れている。
特に以下のような意義がある。
- 戦争で一般市民(特に若者や女性)が犠牲になった現実を伝える
- 「教育の名のもとに動員された」学生たちの悲劇を考える
- 沖縄の歴史と、日本の戦争責任について深く考える場
証言に共通する特徴
「証言」は、ひめゆり学徒隊の生存者たちが自らの体験を語ったもので、沖縄戦のリアルで深い悲劇を私たちに伝えてくれる非常に貴重な記録。彼女たちの声は、「ひめゆりの塔」や「ひめゆり平和祈念資料館」で紹介されており、ドキュメンタリーや書籍でも数多く取り上げられている。
若さと恐怖
ほとんどの学徒は15〜19歳。まだ子どもに近い少女たちが、突然戦場に送り込まれた。
「先生と一緒なら安全だと思っていた。軍人のそばにいれば大丈夫だと思っていた。」
野戦病院での過酷な看護
傷病兵の処置を任されたが、十分な医療器具もなく、素手での手術介助、負傷兵の排泄や死体処理も行っていた。
「蛆虫がわく傷口をガーゼでぬぐった。叫び声、うめき声が壕に響いていた。」
仲間との別れと死
戦況が悪化する中、友人や教師が次々と亡くなり、目の前で命を落とすことが日常になっていった。
「さっきまで隣で笑っていた友達が、急に砲弾で吹き飛ばされた。」
「解散命令」とその後の混乱
6月18日、軍から突如「解散命令」が出され、壕を出て自力で逃げるよう指示される。これにより多くの学徒が戦場に放り出され、帰らぬ命となった。
「壕を出た瞬間、砲弾の雨が降った。どこにも逃げ場なんてなかった。」
今を生きる後悔と願い
生き延びた生徒たちは、自分が生き残ったことへの罪悪感(サバイバーズ・ギルト)を抱えながらも、後世に平和の大切さを伝えようと語り部として活動している。
「あの日のことを話すのは本当につらい。でも、語らなければ、また繰り返されるかもしれない。」
ひめゆり平和祈念資料館の「証言映像室」
館内には、生存者の証言を映像で見ることができるコーナーがある。実際の声、表情、言葉を通して、その時の空気を肌で感じられる。
- 映像証言の中には、名前も明かして自らの体験を細かく語る方もいる。
- 資料館は、証言をアーカイブ化し、未来の世代にも伝わるように尽力している。
関連書籍・映像
- 書籍:「ひめゆりの少女たち」(吉永小百合の朗読でも知られる)
- 映画:「ひめゆりの塔」(1953年版、1995年版など)
- ドキュメンタリー:「証言:沖縄戦とひめゆり」などNHK制作も多い
心に残る言葉
「死ぬことよりも、友達を見捨てることが何より怖かった。」
「戦争は、若い命を一瞬で奪う。生きることの意味を、教えてくれる。」
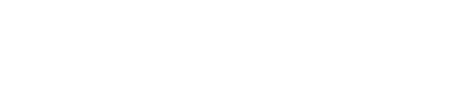





コメント