
平安座島(へんざじま)とは?
平安座島は、沖縄本島の東側に位置する小さな島で、うるま市に属している。沖縄本島と橋でつながっており、車で簡単にアクセスできる。
平安座島(へんざじま)は、沖縄県うるま市の東部に位置する島で、近隣の宮城島、浜比嘉島、伊計島などと並び「与勝(よかつ)諸島」の一部を構成している。この島は、古代からの人々の暮らしや、戦後の石油産業、そして現在に至るまでの変遷において、重要な歴史を持つ場所。
平安座島の歴史
古代〜琉球王国時代
- 与勝半島や周辺の島々と同様に、縄文時代以降の遺跡が点在し、古くから人が住んでいたことが分かっている。
- 琉球王国時代には、農業や漁業を中心とした島民の生活が営まれており、特に海上交通の要所としても機能していた。
- 「与那城間切平安座村」として行政区画の一部。
戦前・戦中の生活
- 小規模な農村・漁村で、サトウキビや海産物を中心にした自給的な経済。
- 太平洋戦争末期、沖縄戦では本島南部ほどではないにしろ、空襲や米軍の上陸に備えた動員などで島民も影響を受けた。
戦後の大きな転機:石油基地の建設(1970年代)
- 1970年代前半、平安座島は日本復帰直前に一大産業地帯へと変貌する。
- 平安座沖石油基地計画により、島の南側を埋め立てて、海上石油備蓄基地(通称:平安座基地)が建設された。
- 日本国内でも最大級の石油貯蔵施設の一つであり、当時は国家プロジェクトともいえる規模。
- これにより、島には工事関係者・労働者が集まり、一時的に活気を見せた時代がある。
橋の開通と生活の変化(1971年〜)
1971年:「海中道路(かいちゅうどうろ)」が開通。これにより平安座島は沖縄本島と陸続きとなり、生活や経済に大きな影響を与えた。
- 島の人々の移動や物流が飛躍的に改善され、都市部との接続が容易になった。
- 周辺の伊計島や宮城島などへも次々と橋が架けられ、与勝諸島は一つの生活圏となる。
現在の平安座島
- 石油備蓄基地の存在は今も続いており、島の産業の中心に位置しますが、以前に比べて人の出入りは少なくなっている。
- 観光はそれほど発展していませんが、海中道路を通るドライブコースの中継地点として知られている。
- 地元の伝統行事やエイサーも残されており、歴史と現代が融合した場所。
象徴的な意味
平安座島は、沖縄の中でも特に「近代化と伝統」「産業と自然」という二面性を持った島であり、沖縄の戦後史を語る上で重要な役割を果たしています。
基本情報
- 所在地:沖縄県うるま市
- 周囲:約7km
- 人口:数百人程度(変動あり)
- アクセス:那覇空港から車で約1時間半
※沖縄本島→海中道路→平安座島へ行ける
海中道路とアクセス
平安座島は、海中道路(かいちゅうどうろ)という有名な道路を通ってアクセスできる。
この道路は、海の上を走る全長約5kmの橋・道路で、ドライブコースとしても人気!
- 海中道路の途中には休憩所や道の駅もあり、絶景が楽しめる。
- 海の透明度も高く、晴れた日は絶景!
観光・見どころ
平安座島自体は観光地としては静かでのんびりした雰囲気だが、周辺の離島も合わせて観光できる。
周辺の人気スポット
- 浜比嘉島(はまひがじま):パワースポットとして知られる「アマミチューの墓」が有名
- 宮城島(みやぎじま):塩工場や展望台あり
- 伊計島(いけいじま):美しいビーチで海水浴やシュノーケリングが楽しめる
地元の産業・特徴
- 昔から製塩業が盛んで、周辺では塩づくりが体験できる場所がある。
- 現在は一部に石油備蓄施設などもあり、産業と自然が混在した島。
- 地元の人々はとてもフレンドリーで、のんびりとした沖縄の島時間が流れている。
まとめ
平安座島は「観光地!」というより、のんびりした沖縄の島暮らしを感じられる場所。ドライブや島めぐりの拠点にもぴったり。人混みを避けたい人には最高の場所。
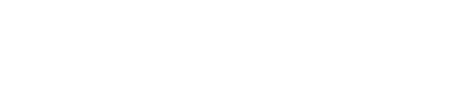





コメント