
沖縄の「旧海軍司令壕(きゅうかいぐんしれいごう)」は、第二次世界大戦末期の沖縄戦において、日本海軍の司令部が置かれていた地下壕(トンネル)である。正式には「海軍司令部壕」とも呼ばれ、現在は平和学習や戦争の記憶を伝える史跡として一般公開されている。
基本情報
- 名称:旧海軍司令壕(海軍司令部壕)
- 場所:沖縄県那覇市の南にある豊見城市(旧:小禄地区)小禄森(オロクモリ)と呼ばれる丘の下
- 建設時期:1944年頃(昭和19年)
- 運用部隊:日本海軍 沖縄方面根拠地隊
- 司令官:大田實(おおた みのる)少将
歴史背景
沖縄戦(1945年)の際、沖縄本島の防衛は日本陸軍第32軍が主に担っていったが、海軍も独自に防衛組織を持っていた。その司令部がこの壕に置かれ、大田實少将を司令官とする約400名の海軍兵がここに駐屯していた。
壕は地元住民などにより手掘りで掘られ、長さは約450メートル(現存部分は約300メートル)、作戦室、通信室、幕僚室、医務室、自決の間などが設けられていた。
悲劇的な最期
1945年6月13日、大田少将は壕内で壮絶な最期を迎えた。アメリカ軍の侵攻が激化する中、彼は壕内で自決を遂げる。自決に先立ち、海軍次官宛てに打電した電報はとても有名で、次のような内容が含まれている:
「沖縄県民かく戦えり、県民に対し後世特別のご高配を賜らんことを」
この言葉は、沖縄県民がいかに困難な中で懸命に戦い、生き延びようとしていたかを伝えるものとして、今も語り継がれている。
現在の様子
現在、旧海軍司令壕は「海軍壕公園」として整備されており、壕の一部が公開されている。
主な見どころ:
- 壕内の見学ルート(復元された作戦室・幕僚室など)
- 自決の部屋(壁に残る手榴弾による痕跡)
- 記念資料館(当時の写真や手紙、兵士の遺品など)
- 慰霊碑(壕の上部の公園に設置)
意義
旧海軍司令壕は、沖縄戦の実態を知る貴重な史跡であり、「平和の大切さ」や「戦争の悲惨さ」を後世に伝える場として、多くの修学旅行生や観光客が訪れる。
沖縄県豊見城市に位置する旧海軍司令部壕は、太平洋戦争末期の沖縄戦において、日本海軍の司令部が置かれていた地下壕である。現在は「海軍壕公園」として整備され、戦争の悲惨さを伝える貴重な史跡として一般公開されている。
見学ポイント
1. 地下壕内部(全長約300m)
- 司令官室:大田實少将の辞世の句が壁に刻まれている。
- 作戦室・幕僚室:当時の指揮が行われた部屋が再現されている。
- 自決の間:手榴弾による自決の痕跡が壁に残されている。
- 壕内通路:つるはしで掘られた跡が生々しく残り、当時の過酷な状況を感じ取ることができる。
2. 資料館
壕の入口付近に位置し、当時の写真、兵士の遺品、戦況図などが展示されている。戦争の実態を学ぶことができる貴重な資料が揃っている。
3. 慰霊之塔
壕の上部にある公園内に設置された慰霊碑で、戦没者の冥福を祈る場所として訪れる人々が絶えない。
周辺の関連史跡
1. 平和祈念公園(糸満市)
沖縄戦終焉の地である摩文仁の丘に位置し、平和祈念資料館や各都道府県の慰霊碑が設置されている。
2. ひめゆりの塔(糸満市)
学徒看護隊として動員された女子学生たちの慰霊碑で、隣接する「ひめゆり平和祈念資料館」では彼女たちの証言や遺品が展示されている。
3. 前田高地(浦添市)
沖縄戦で激戦地となった場所で、現在は「浦添城跡」として整備され、戦跡としての説明板が設置されている。
アクセス情報
- 住所:沖縄県豊見城市字豊見城236番地
- 開館時間:9:00~17:00(最終入場16:30)
- 休館日:年中無休(臨時休館を除く)
- 入場料:大人450円、小人230円
- アクセス:那覇空港から車で約15分。公共交通機関を利用する場合は、那覇バスターミナルからバスで「豊見城中央病院前」下車、徒歩約15分。
旧海軍司令部壕を訪れることで、戦争の悲惨さや平和の尊さを深く感じ取ることができる。周辺の関連史跡と併せて巡ることで、より一層理解を深めることができる。
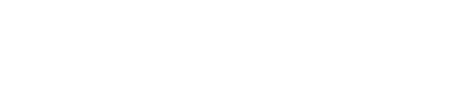





コメント